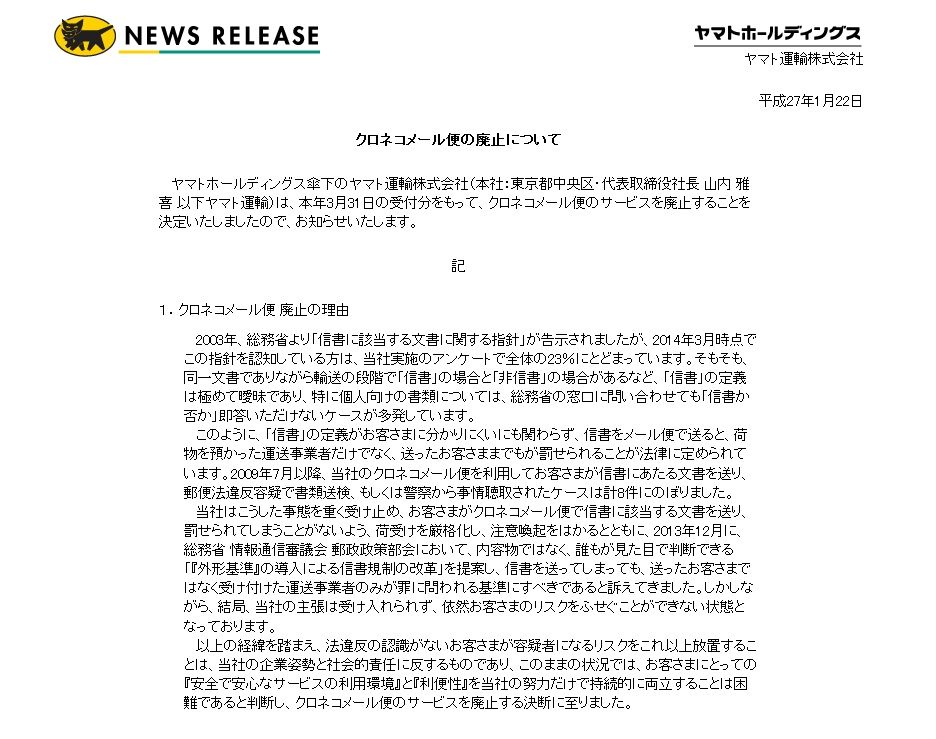2015年8月16日日曜日
Crown Athlete Turbo
"いつかはクラウン"
いま話題の某デザイナーの作品の一つである"TOYOTA Re BORN"をバックに佇んでいるピンクの乗用車。
トヨタが1955年より生産している高級車、クラウンの14代目。通称210系です。
210系クラウンは2012年12月に先代に当たる200系からフルモデルチェンジをし、既に2年以上経過しています。
クラウンは法人利用も少なくなく、またロングセラーモデルということもあり非常に販売台数の多いクルマです。
近年自動車のモデルサイクルが長くなったにも関わらず、現在でもおおよそ4年一回フルモデルチェンジを繰り返しているまさにトヨタのフラッグシップモデルであります。
ちなみに4年でフルモデルチェンジの理由には、1988(昭和63)年7月以前の車検制度が関係していました。
現在は新車登録から初回の車検までは3年ですが、'88年6月30日までに登録された自家用乗用車であれば新車、中古車に関わらず2年でした。
その為、おおよそ発売から2年でマイナーチェンジ、4年でフルモデルチェンジを行えば車検を理由に自動車が売りやすくなるという営業的観点からこのモデルサイクルが生まれたようです。
もちろんクラウンのように販売台数が見込めるクルマの場合、多額の費用を投じて新型車を投入することは利益に繋がりますが、近年、若者のクルマ離れや不況等で新車販売台数が落ち込んでいる事に加え、初回車検までの期間が3年に伸びた等の理由からモデルサイクルも伸びていったように考えられますね。
このモデルサイクルを今でも守り続けているクラウン、前述の通り発売から2年以上経過している210系にもマイナーチェンジの話が飛び込んできています。
来る10月1日、デザインの小変更、ボディカラーの追加に加え、搭載エンジンの変更等のマイナーチェンジが予定されているようです。
現在の210系クラウンのエンジンラインナップは2GR-FSE、4GR-FSEの排気量の異なる二つのV6と、ハイブリッドモデル用の2AR-FSEの直4という2種類3排気量となっています。
3,500ccの2GR-FSEはアスリートに、2,500ccの4GR-FSEはアスリートとロイヤル、ロイヤルサルーン、そして2,500ccの2AR-FSEはアスリートハイブリッド、ロイヤルハイブリッドに採用されています。
今回のマイナーチェンジでは2,500ccのアスリートに採用されている4GR-FSEが、現在レクサスNX200tやIS200tに搭載されている8AR-FTSに変更になるようです。
この8AR-FTSというエンジンは2,000cc直列4気筒DOHC直噴ターボエンジンという小排気量ターボエンジンであり所謂"ダウンサイジング"となるわけですね。
この8AR-FTSの搭載されているNX200tはFF横置きレイアウトですが、その後に発売されたIS200tはFR縦置きレイアウトとなっており、そのユニットがほぼそのままクラウンにも搭載される事となりそうです。
またトランスミッションもIS200tに搭載されている8速SPDS(Speed Sport Direct Shift)が採用されるようです。
最高出力は235ps/5,200~5,800rpm
最大トルクが35.7kgm/1,650~4,000rpmと数値だけ見ると、3,500ccの2GR-FSEにも匹敵するパワフルなトルクが印象的ですね。(2GR-FSEは38.4kgm/4,800rpm)
またターボ専用に開発されたD-4STに加え、より可変範囲の広い連続可変バルブタイミング機構VVT-iWを採用したことにより、JC08モード燃費は13.4km/L(IS200t)をマーク。
6月に追加された同じく2,000ccターボの日産のスカイライン200GT-tとまさに同クラスとなりますね。
こちらのスカイラインも"スカイライン2000GT"の復活と巷で話題になりましたが、クラウンのターボも170系の1JZ-GTE搭載モデル"アスリートV"の生産終了以来、12年ぶりの復活となります。
またマイナーチェンジでトヨタのスポーツカーブランドである"G's"も新たにラインナップに加わるようです。
現在販売されている主にプラットフォーム等を共有しているマークX G'sとチューニングメニューはほぼ同じとなりそうですね。
エクステリアも他のG'sモデル同様、専用のLEDランプやホイール等があしらわれ精悍なフォルムとなっています。
マフラーもやはりマークXのような4本出しとなるのでしょうか。
ちなみにこのマイナーチェンジによって2003年発売の180系からラインナップされ続けてきた、アスリートのV6 2,500cc 4GR-FSE FRモデルは消滅してしまいます。(4WDは継続生産)
"ゼロクラウン"の登場から早12年。
高級車の代名詞的存在でもあるクラウンも、また一つ時代の流れで大きく変わりそうですね。
ターボエンジンはかつてのハイパワーだけが取り柄のイメージとは打って変わり、今や小排気量ターボエンジンこそ環境にも良く、燃費の向上にも一役買っているというまさにガソリンエンジンの行き着く先でもあります。
サイズは小さく、しかしパワーが大きく、重量も軽く、燃費も良い、むしろ大排気量エンジンの方が劣っているのは明確ではありますが、自動車のステイタス性という面から見ると、大排気量エンジンには大排気量エンジンの良さがありますよね。
今後国産車もダウンサイジングターボエンジンのクルマが増えて行く事と思いますが、どこか寂しさも感じてしまうのは私だけでしょうか。
2015年7月14日火曜日
[FM5]NA8C ROADSTER
1994 Mazda MX-5 Miata (NA8C)
Over Rev! Yoshinaga's Roadster
エンジン型式:BP-ZE
最大出力:180ps(132kw)/6,500rpm
最大トルク:20.0kgf-m(196N-m)/4,500rpm
種類:直列4気筒DOHC
総排気量:1,839cc
過給器:自然吸気
車両重量:1,072kg
女性版頭文字Dなどと評される、峠やサーキットを舞台にレースを繰り広げる自動車漫画"オーバーレブ!"に登場する、"吉永"という男性キャラクターの愛車をモデルにしています。
オーバーレブ!をご存じの方は、リアバンパーに大きく貼られたダンロップステッカーで思い出される方も多いのではないでしょうか。
ちなみにオーバーレブ!の作者山口かつみ氏は福岡県北九州市の出身で、現在も在住しているんだとか。
私も北九州市に比較的近い地域で生活しておりどこか親近感を覚えます。
福岡県の出身故か、オーバーレブ!の舞台は神奈川県ながら、福岡県の有名な心霊スポットの一つでもある"犬鳴峠(いぬなきとうげ)"をモデルとした"犬鳴峠(いんなきとうげ)"なる幽霊騒ぎのある峠が作中に登場しています。
ちなみに実際の犬鳴峠ですが、新道と旧道があり、新道の方は至って特徴の無いただのトンネルです。
旧道は現在は使われておらず、入口がいたずら防止の為にブロックで塞がれており、旧道に繋がる道はフェンスが張られており、基本的に立ち入りは出来なくなっています。
ちなみにこの犬鳴峠は宮若市という地域と糟屋郡久山町という地域をつなぐ為のものであり、双方の市町に跨っています。
旧道を訪問する際に糟屋郡久山町の方から侵入した場合は、処罰の対象となるのでご注意を。
犬鳴峠がここまで有名な心霊スポットとなってしまったのは、およそ30年ほど前に、いわゆる不良グループによって一人の男性が旧道で焼殺された事件が由来となっているのではないかと言われています。
また15年ほど前にも犬鳴峠近くの犬鳴ダムにおいて死体遺棄事件が起こっているのも追い風になってしまったのではないでしょうか。
人が殺されている事からお化けが出るなどと言われ、次第に面白おかしく犬鳴村伝説などという話が作り上げられてしまったのでしょうね。
またちょうど都市伝説ブームの時期というのもあって瞬く間にメディアによって日本全国に広まったのではないのかなと思います。
ちなみに福岡県民の私として言わせて頂くと、もちろんお化けなんてでませんし、犬鳴村伝説も全くのガセです。
県外から旧道を訪問される方も大勢いるようですが、お化けよりいわゆる"筑豊のDQN"に警戒された方が吉かと思われます。
さて、話が大きく脱線しましたが、このNA8CはForza Motorsport 5では最も低いクラスであるDに照準を合わせてセッティングしてみました。
DクラスではBMCミニや、ロータスエランといったロードスターよりも遥かに小さく、軽い車の活躍している場であり、敢えてここはあまり軽量化に重点をおかず、バランスの良いセッティングを目指しています。
また、敢えてちょっとしたこだわりとして機械式LSDを入れずに、NA8C純正のトルセンLSDをそのまま使っています。(果たしてForza Motorsport 5が純正LSDの性能をどこまで再現しているのかは分かりませんが)
Dクラスは競技人口が少ないというのもありますが、十分オンラインでも戦える1台になっていると思います。
残念ながらBMCミニには及びませんが、私より速い人の手にかかれば着いて行く事も不可能ではないと思われます。
Circuit de Catalunya 参考タイム
2:11.318
2:20.534 (Stock)
1/4 mile : 14.583
1/2 mile : 23.334
1 mile : 37.384
チューニングデータ名 : D400 MX-5
キーワード1 : サーキット
キーワード2 : ハンドリング重視
フリーワード : Final 4.77
チューニングデータ名 : D400 MX-5 Ver.2
キーワード1 : サーキット
キーワード2 : ハンドリング重視
フリーワード : Final 4.(スペース)55
基本はファイナル4.77です。
レース仕様のミッションを入れているので6速まであるのですが、5速で吹け切れるようにクロス化しており、5速と6速は同じギア比にしている為、実質5速になっています。
180馬力しか無い為、ほぼ全てのコースは4.77で問題無いのですが、ノルドシュライフェのメインストレートとサルテサーキットのオールドミュルサンヌレイアウトでのユノディエールだと頭打ちになるので、若干ハイギア仕様の4.55も用意しています。
バーサストのバックストレートを抜けてヘアピン手前の若干下った所でもレブに当たりますが、中盤の高低差の激しいセクションを考慮すると4.77で大丈夫かと思います。
ちなみに外装は前述の通り、オーバーレブ!の吉永のロードスターをモデルにしている為、Garage VARYのフロントリップ、サイドスカート、リアバンパーに、5ZigneのGN+の16インチをハイグリップラジアルと組み合わせています。
Forza Motorsport 4の頃も同じような車に乗っていたんですね。
ろど☆すたなだけに…。
2015年6月19日金曜日
[FM5]PETRONAS GS350 ST3
2013 Lexus GS 350 F Sport (DBA-GRL15)
C500 PETRONAS GS 350 ST3
エンジン型式:2GR-FSE
最大出力:320ps(235kw)/6,400rpm
最大トルク:39.5kgf-m(387N-m)/4,800rpm
種類:V型6気筒DOHC
総排気量:3,456cc
過給器:自然吸気
車両重量:1,788kg
モデルは2012年にOTG Motorsports(大阪トヨペットグループ)がスーパー耐久ST3クラスに参戦していた、PETRONAS TWS GS350(S191)です。
Forza Motorsport内に於いても、出来る限りSTOの技術規則に則ってチューンナップしています。
またサスペンションは実際にTOM'sがリリースしているスポーツサスペンションキット(S191)のバネレートを流用。
トランスミッションもスープラ(JZA80)に採用されていたトヨタとゲトラグの共同開発によって生まれたV161(後期型RZ)のギア比に、ソアラ(Z3*)の5MT車用のファイナルを組み合わせて流用し最適化しています。
Circuit de Catalunya 参考タイム
2:06.859
2:15.677 (Stock)
チューニングデータ名 : ST3
キーワード1 : サーキット
キーワード2 : ハンドリング重視
フリーワード : Japan Super Taikyu ST3
2015年5月29日金曜日
Logicool Keyboard K120
こんばんは、ろど☆すたです。
今回の記事よりキーボードを変えてみました。
Logicool Keyboard K120
キーボードやマウスにはこれと言った拘りもなく、昨日まではエレコムの至って普通の数百円の物を使っていました。
何故このタイミングでK120の購入に至ったかというと、近所の家電量販店がリニューアルの為現在セール中とのことで立ち寄ってみたのです。
お目当ては他の物だったのですが、ワゴンに山積みにされたキーボードが目に入りました。
K120の上位機種に当たるものもいくつかあり、売り尽くしとのことで某インターネットショッピング大手にもひけをとらない価格で、もはや投げ売り状態でした。
せっかくなのでこの際奮発して上位機種であるK270を買おうかなと思いましたが、無線なんですね。
今の時代ワイヤレスが当たり前ですし、むしろ有線なんて今時っていうイメージなのかもしれませんが、私はよっぽどのことがない限り有線にしておきたい性分でして。
その一番の理由としては有線ならば電池が必要ないということ。
Xbox 360やWiiのコントローラーは無線で駆動させる際に単三乾電池が2つ必要でした。
充電池を使用してはいたもののやはり消費量がそれなりに大きいですし、そもそも電池が減ってくると反応が鈍くなったり振動が弱くなったりと非常に不便なんですよね。
その点有線はもちろん電池切れ、接続切れという心配はなく、常にフルパワーの動作が保証されます。
それに無線の場合電池本来の重さがプラスされますからね。
それ故にXbox OneのコントローラーはUSB接続で有線化して使っています。
キーボードもそういう点からやはり有線を選びました。
もちろん時と場合によっては無線のほうが優位な場合は大いにありますけどね。
ただ私の環境においては無線であるメリットよりもデメリットの方が多く感じられた為にK120をチョイス。
K120ですが、有線キーボードとしては高い評価を得ている商品らしく、確かに非常にタイプし易いですし反応も抜群に良いです。
キーのストロークは浅めですが、それぞれのキーが独立している故にタイプミスも最小限に抑えることができそうです。
この辺は個人の好みではありますが、私はどうしてもノートパソコンのキーボードのようなフラットなタイプが苦手でして、強いて言うならばK120ももう少しストロークが深くても良いかなという印象です。
キーボード本体の作りもしっかりとしていて普通にタイピングする分にはブレることもなくカッチリとした印象を覚えます。
キーボードのバンクについてはレッグを寝かせた状態のフルフラットと、レッグを立たせた状態の弱バンク状態の2段階です。
レッグを立たせた状態は他の一般的なキーボードと差異なく、これがスタンダードかなという感じですね。
シフトやスペースといったキーのサイズもこれと言った不満もなく、端をタイプしてもしっかりと認識してくれるので、多くの人に対応した作りになっているかと思います。
キーのタイピング音ですが、私としては非常に静かだなと思いました。
ただ、他のレビューなんかを読むと、静かなところで多少気になるレベル、といったような表記も見られますし、数万円するようなキーボードと比べた時にはやはりうるさいのかもしれません。
唯一私が気になった点としては、キーのプリントといいますか、文字ですね。プリントではなくデカールのようです。
よく見ると気がつくのですが、キーに文字がプリントされているのではなく、真っ黒のキーに上から文字のデカールが貼られています。
現状目を凝らさなければ気になりませんが、使用していくうちに剥がれたりズレたりが多少心配ではありますね。
無いなら無くても構いませんが。
2013年3月リリースのWindowsOS対応、USBキーボード、K120でした。
2015年4月15日水曜日
Daydream Believer
こんばんは、ろど☆すたです。
ずっと夢を見ていまもみてる
僕はデイドリームビリーバーそんで
彼女はクイーン
一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
1989年の忌野清志郎率いる覆面バンド"タイマーズ"のヒット曲。
元々はアメリカのビートルズに対抗したバンド"モンキーズ"の自身2番目のヒット曲で、1967年にビルボード1位を飾っています。
モンキーズのデイドリームビリーバーとタイマーズのデイドリームビリーバーは、リズムこそ同じものの歌詞の意味は大きく異なっており、ZERRY(忌野清志郎)によって書かれたなんとも言えない哀しさや愛を感じさせられる詩は今なお支持を得ています。
そんなタイマーズのデイドリームビリーバーは日本ではモンキーズの原曲以上に有名となり、発売から25年以上経つ今日でも多くの場面で使用されています。
テレビCMにもコンスタントに起用され、現在では2011年から継続してセブン&アイホールディングスのCMに使用されています。
何故4年にも渡って同じ曲を使い続けているのか、疑問に思う人も多く、中にはセブン&アイホールディングスお客様相談室に問い合わせた方もいるようです。
セブン&アイホールディングスの解答には、時代に左右されない曲であること、社員、客、共に支持されていること、といった内容が挙げられたそうな。
純粋にデイドリームビリーバーの歌詞を見れば、すごく切なくも愛しくも感じられるような、まさに時代に左右されず、多くの人に受け入れられるような曲ですよね。
ただ、忌野清志郎はあくまでロックミュージック。デイドリームビリーバーを歌っている容姿は皮肉でもあり、チェルノブイリ事故の際に真っ先に原発反対を訴えていた反体制派を貫いてきた人物でもあります。
決して忌野清志郎を否定するわけでも侮辱するわけでもないのですが、セブン&アイホールディングスという日本の大企業が敢えて、タイマーズのデイドリームビリーバーを長きにわたってCMに起用し続ける理由とは、上述の内容だけなのでしょうか。
ちなみに私自身、セブン&アイホールディングスがデイドリームビリーバーを起用し続ける理由は、皮肉抜きで単に会長鈴木敏文氏の個人的な好みかと思っていました。
今やコンビニエンスストア業界最大手となったセブンイレブン。
一つの店舗に置ける商品数にはもちろん限りがありますし、その中で売れ筋死に筋をいち早く見分け入れ替えて行かなければなりません。
もちろんそれは各店舗のオーナーや店長の仕事でもあるのですが、セブンイレブンジャパンでも推奨商品、推奨取り消し商品を設定して各店舗へ入れ替えを促しています。
特にその中でも入れ替わりが激しいのがドリンク類とアイス類。
しかしその入れ替わりが激しい中でも、セブンイレブン全店舗に必ず置いてあるアイスがあるんだとか。
ガリガリ君。
以前、セブン&アイホールディングス会長の鈴木敏文氏とそのお孫さんが二人で、会長宅近所のセブンイレブンにお孫さんの好物というガリガリ君を買いに行った時のこと。
偶然その店舗にはガリガリ君がなかったんだとか。
そこで激怒した鈴木会長はその場でセブンイレブン全店にガリガリ君を置くことを命じた、と。
あくまで噂にすぎませんが、確かに私の知る限りではガリガリ君の無いセブンイレブンは見た記憶がないように思います。
それ以前に、セブンイレブンに限らず、ガリガリ君の無いコンビニやスーパー自体が珍しい気もしますが。
数年前よりセブンイレブンジャパンと赤城乳業は提携してガリガリ君を開発・販売していることからもそういう話が生まれたのかもしれないですね。
また、ガリガリ君のコーンポタージュ味を会長が試食したところ口に合わなかったのか、突如全廃棄なんていう事でも話題になっていたのが記憶に新しいです。
鈴木敏文会長とガリガリ君との話題は今後も尽きそうにないですね。
2015年4月5日日曜日
Forza Horizon Presents Fast & Furious
こんばんは、ろど☆すたです。
Forzaシリーズにはドライビングシミュレーターとしての色の強いMotorsportと、オープンワールドのHorizonの2つのバージョンがあります。
そのHorizonの最新作、Forza Horizon 2をベースに作成されたスタンドアローン版DLC、「Forza Horizon Presents Fast & Furious」が先月27日より期間限定で無料で配信されています。
日本では4月17日より公開される人気カーアクション映画の最新作「ワイルドスピード SKY MISSION(原題: Fast & Furious 7)」の公開を記念して、配給元のユニバーサルピクチャーズとマイクロソフトがパートナシップを結び、Xbox One、Xbox 360両ハードで配信されています。
宣伝を兼ねてか4月10日までは無料配信、その後も$10と比較的お求めやすい価格での配信となっています。
また先述の通りスタンドアローン版(別のソフトに依存しない)の為、Forza Horion 2を持っていないプレイヤーでもすべての機能を楽しめるようになっています。
むしろForza Horion 2の豪華なデモと言っても良いのではないでしょうか。
現に私はForza Motorsportシリーズは2以降全てプレイしているものの、Horizonシリーズは未体験なので良い機会になりました。
登場する車がワイルドスピードSKY MISSIONにちなんでいるだけで、基本的なゲームシステムはほぼForza Horizon 2なんだとか。
ゲームの内容としては、ワイルドスピードX2以降天才メカニックとして登場する「テズ・パーカー」にトランスポーターとして雇われ、Forza Horizon 2の舞台でもあるフランス南部の都市、ニース近郊でストリートレースやミッションをこなし10台の車を集めていくというもの。
普通にプレイしていけば2~3時間でコンプリートでき、実績もほぼストーリーを進めて行くだけで解除できるものばかりなので、飽きる間もなく終わってしまったという印象です。
Horizonシリーズは未体験ですが、やはりForzaを名乗っているだけあって、グラフィックや車のモデリング、サウンドは流石ですね。圧巻です。
挙動に関してはMotorsportよりもドリフトしやすくなっている印象を受けました。
またワイルドスピードを題材にしている故か、全車とても性能が上げられており、300km/hオーバーの世界の爽快感はすごいですね。
また、Motorsportにはない未舗装路が多くあったり、バサーストヘリや輸送機といった車以外の乗り物とも対戦できたりと、ワイルドスピードのように"カーアクション"的要素がふんだんに盛り込まれています。
この辺りはForza Horizonそのものでもありますね。
ちなみにフォトに幾度と登場している白いJZA80スープラは、劇中にももちろん登場するのですが、ワイルドスピードシリーズに於いてブライアン・オコナー役を演じていた故ポール・ウォーカーの一番お気に入りの実際の所有車でもあったんだとか。
ワイルドスピードSKY MISSIONの撮影途中に事故によって40歳の若さで亡くなったポール・ウォーカーの代役は、実の弟であるコディ・ウォーカーが務めることとなり、完成までたどり着きました。
新作SKY MISSIONは時系列的にはワイルドスピードX3 TOKYO DRIFTの次に当たるようで、舞台は東京からスタートするそうです。
2015年3月30日月曜日
Forza Motorsport 5
こんばんは、ろど☆すたです。
ツーリストトロフィーからのホンダ・フォルツァではありません。
昨年9月に日本でも発売された、マイクロソフトのXbox OneとForza Motorsport 5を遅ればせながら購入致しました。
もともとForzaシリーズはXbox 360のForza 2からプレイし続けているのですが、Xbox Oneローンチ当時、本体とソフトを揃えられる程の大金をポンと出す余裕が無かったため泣く泣くスルーしていました。
あれから半年程経ち、Twitter等でも度々Forzaの話題が上る度に購買意欲が増しまして、遂に購入に踏み切ってしまいました。
2009年にお年玉でXbox 360を買った時から早6年。
Xbox 360末期はほぼForza専用機となっていましたが、遂に自分で稼いだお金(アルバイトではありますが)でゲーム機が買えるようになったのだと思うと感慨深いものもありますね。
先ずXbox Oneですが、サイズは360より一回りくらい大きいでしょうか。
そしてかなり静かになりました。
先述の通り'09モデルのアーケードの為、Xbox 360の中でも古い方の部類になるのでより一層静かになったと感じるのかもしれません。
ちなみに今さらではありますが、よく6年間、一度も故障せずに頑張ってくれたなと思います。
Xbox 360はそもそも信頼性にかなり問題があったハードでありますし、使用頻度もそれなりに高かったと思います。
偶然良いタマを引き当てたのかもしれませんが、本当にうちのXbox 360には感謝です。
(信頼性に問題があったのは主に型番がB4Jから始まる最初期のモノのみという見解もありますが)
コントローラーも多少変更があり、トリガーのストロークが若干少なくなったかな、と感じました。
その分トリガーにもモーターが入り振動するようになった為、テールがスライドしそうになる時や、ブレーキがロックしそうになる時にトリガーからフィードバックしてくれます。
また360のコントローラーは無線のものと有線のものが売られていましたが、Oneでは一つのコントローラーで無線のみでなく、SonyのDual Shock 3のようにマイクロUSBで本体と接続することで有線としても使用できるようになりました。
これは便利だなと思います。
肝心のForza 5ですが、やはり次世代機という事あってグラフィックには驚きましたね。
初めてForza 4をプレイした時にも感動しましたが、5をプレイしてしまった今見るとどうしても色褪せてしまいます。
挙動に関しては基本は変わらず、タイヤの限界がより低くなったように感じました。
2からしかプレイしたことはないのですが、2が一番ピーキーだったイメージがあります。
3になってタイヤのしなりを実装した故か突然グリップレベルが格段に上がり、その後4、5とまた少しずつグリップが落ちて行っているように感じます。
とはいえども私は実際の車の運転経験が無い為、果たしてどの挙動が一番リアルなのかは分かりかねますが。
ただ、5では縁石に乗った状態でのフルブレーキングや、エスケープゾーンへの脱輪等よりシビアになっているようにも感じました。
また5の目玉でもあるドライバター。
ドライバターとはプレイヤーの実際の走りを分析し、名前と特徴をそのままAIとして登場させるというような機能のことです。
厳密にはAIと言っていいのか微妙なラインではありますが、実際4以前のAIにもそれぞれ特徴と個性が実装されていたのも事実です。
5ではよりその精度を上げて、さも実際のプレイヤーと走っているかのような錯覚に陥らせてくれます。
これがまたかなり白熱するんですよね。
毎レース最大5名(自車含め全16名中)のフレンドのドライバターが登場するのですが、3や4の頃にオンライン対戦していた方のドライバターはまさにそのまま走るんです。
ドライバターのレベルを上げると、オンライン対戦でもあと一歩のところで勝てなかったフレンドに、ドライバターでもあと一歩で勝てない、なんていう最高に白熱したバトルが楽しめるので、今のところオフラインばかりやっています。
4に比べて車種やコースが減っていたり、ソート機能が不便だったりと本国ローンチタイトル故か、中途半端さも否めませんが、それ以上にドライバターとグラフィック、サウンド、そして運転する楽しさが勝っていて、Xbox OneをForza専用機と見ても十分良い買い物だったのではないかと思います。
Forza 5をプレイされている方とご一緒出来れば嬉しいです。
Xbox One ゲーマータグ: Roadstermx5R
2015年3月6日金曜日
PlayStation2をD端子で
こんばんは、ろど☆すたです。
先日ps2ソフト"ツーリストトロフィー"を購入しちょこちょこ遊んでいたのですが、液晶テレビにコンポジット接続故、文字が潰れたり滲んだりしている点が気になっていました。
そこで少しインターネットで調べてみると、ツーリストトロフィーはプログレッシブに対応しているではありませんか。
そこで購入したのがこちら。
デイテル・ジャパン PS3/PS2用 D端子ケーブル "美接続"
サードパーティ製ではありますが、こういう部分はソニー製だから良いという訳でもないですし、amazonでのレビューも良かったのでデイテルの製品にしてみました。
商品到着後早速接続してみたのですが、音声は出るものの画面は真っ暗!
繋ぎ直してみたり、端子に息を吹きかけてみたり(良くないようですね)してみましたが真っ暗なまま。
試行錯誤の結果、あらかじめコンポジット接続をしている状態でps2ダッシュボードから映像出力をRCBからY/Cb/Pb/Cr/Prに変更してからD端子で接続すると無事表示されました。
改めて考えてみれば、ps2本体はRCBで出力しているのにY/Cb/Pb/Cr/Prで表示させようなんてのは無理なことですよね。
接続後はそのままソフトを起動し、ゲームの設定から画面サイズを16:9、映像出力を1080iにすることで見違えるように綺麗になりました。
ただ私の環境によるものなのかもしれませんが、テレビやps2本体近くの電気の電源のON/OFF等で一瞬チラつきが確認できました。
レース中でも気にならない程度ですが、一応肉眼で気がつくレベルではありました。
ちなみにD端子、今となってはもはや過去の遺物のような存在でも有りますが、HDMIが普及する前まではアナログ接続で最もきれいな端子とされてきました。
D1からD2、D3、D4、D5まであり、数が大きくなるほど大きな解像度に対応しており、D2はD1、D3はD1、D2といったように下位のバージョンも含めて表示することができます。
ps2はD1(480i)、D2(480p)、最も解像度が高いものでD3(1080i)が限界、
ちなみにps3はD5(1080p)からHDMIにかけて対応しているようです。
ここでよく見かける480pだとか1080iなどの数字ですが、意外とこの意味が知られていないようですね。
私も最近まで正直よくわかっていませんでした。
480や1080の数字は出力される映像の縦の解像度のことなんです。
480は640×480から来ています。
このサイズが良く耳にする"VGA"という規格で黄金比とも呼ばれる4:3を採用しています。
1080は1920×1080。こちらは最近の主流でもある"フルHD"と呼ばれている規格ですね。16:9を採用しています。
つまり数字が大きくなればなるほど縦の解像度が上がる、すなわち画面解像度が上がるということになりますね。
ちなみに最近話題になっている8Kと呼ばれる解像度は7680×4320で、4320pとなるんです。
フルHDのおよそ8倍の解像度をいずれはテレビ放送したいようですが、果たしてどうなるんでしょうか。
その解像度の後ろにつくiやpの文字。これはインターレースとプログレッシブの頭文字から来ています。
映像は24コマ/秒、30コマ/秒のいわばコマ送りなんです。
インターレースとはそのコマを奇数と偶数にわけて交互に表示することで映像として流しています。
対してプログレッシブは1つのコマをそのまま切り替えて行くことで映像となります。
テレビ放送は全てインターレースで行われていますが、近年のゲームやブルーレイなんかはプログレッシブになっており、比べて見ると連続して流れる部分等はやはりインターレースだと少しチラつくように見える場合があるようですね。
フルHDとして販売されている現在のテレビは全てプログレッシブの1080pとなってはいますが、テレビ放送がインターレースな為、1080iもサポートされています。
技術的にはやはり1つのコマを高速で切り替えるプログレッシブの方が難しく、D端子も解像度の低いインターレースから順に対応して行ったようですね。
ツーリストトロフィーがリリースされた当時('06年頃)はD3が最先端だったらしく、最大で1080iまで対応になっています。
そもそも古いハードですから多くを求めるのも酷な事ではありますが、少ないながらも他にもD端子出力が可能なソフトはあるようです。
今は亡きサイトのミラーページですが、数少ないプログレッシブ対応ps2ソフトがまとめてあります。
ちなみにツーリストトロフィーのベースであるグランツーリスモ4はもちろんプログレッシブ(D3)対応です。
プログレクラブZ
2015年2月27日金曜日
Tourist Trophy
こんばんは、ろど☆すたです。
グランツーリスモシリーズで有名なポリフォニーデジタルが、以前バイクのゲームを開発していたことをご存知でしょうか。
ツーリストトロフィーです。
2006年にグランツーリスモ4をベースにして発売されたツーリストトロフィー。
私自身二輪車に興味を持ったのがここ数年ということもあり、発売当時は存在すら知りませんでした。
最近になって二輪車に興味を持ったものの、バイクのゲームとなるとmotoGPのような完全プロレース志向のモノが多くイマイチ魅力が感じられませんでした。
しかしひょんなことからツーリストトロフィーの存在を知り、ドリームCB400から当時最新のファイヤーブレードまで収録されている事を知り、気になるようになりました。
ただグランツーリスモほどヒットしたわけでもなく、そもそものバイクファン人口も少ない上に、少々とっつきにくいイメージからか中古と巡りあうのも一苦労。
結局バイトの帰り雨の中原付を走らせ、片道30分以上かかる某レンタルショップまで行ってきました。
518円(税込)也。
平日の午後6時を回った冷たい雨の降りしきる夜、エンプティを指す50ccのスクーターで往復1時間強。
これぞまさにツーリストトロフィー。
ゲームUIはほぼグランツーリスモ4。
しかしBGMは全くの別物のため、グランツーリスモ4をプレイしたことのある身からすると少し違和感を感じました。
BGMは正直イマイチです。盛り上がりに欠けるというかイメージに合わないというか。
ツーリストトロフィーにはプロモードなるものがあり、前後独立してブレーキを操作できるようになっています。
初期コンフィグでは□が前輪ブレーキ、R2が後輪ブレーキに割り当てられており、慣れるまではなかなか難しいですが、ある程度プレイしているうちにむしろ操る楽しさを感じられるようになりました。
もちろん□のみでホンダのコンビブレーキのように前後輪連動するように設定することも可能です。
車種はグランツーリスモシリーズのようにレースに参戦してCrを貯めて購入したり改造したり、というわけではなく、チャレンジモード※やレースイベントのプレゼントカーで手に入れる事ができます。改造は残念ながら簡単なセッティングと、タイヤコンパウンド、マフラーの交換のみです。
(※グランツーリスモ4のミッションレースとスペシャルコンディションレースを足して2で割ったようなもの。条件を満たせばバイクが獲得できる。)
少しその辺のシステムについては残念な面もありますが、リアルさはともかくエキゾーストノートの雰囲気は抜群です。
めちゃくちゃ実車に近いサウンドがするといえば嘘になりますが、2stレーサーレプリカのキンキンとしたサウンド、4stマルチの上まで伸びる甲高いサウンド、どれも非常に心地がいいですしなにより操っている感覚に陥れます。
また、マフラーを変えると外観とそれなりにサウンドも変わるのがなお良いですね。
最初に貼ったフォトはヤマハのグランドマジェスティなんですが、焼き色のついたちょっとアレな感じのマフラーにしてみました。
サウンドもちょっとアレな感じです(
他にも、ヤマハRZ250は細身のサイレンサーのついたイノウエっぽいチャンバーだったり、ホンダCB750Fは耐熱塗装の施されたモリワキっぽい集合管だったりとカスタムしたバイクを眺めるだけでも楽しいです。
グランツーリスモシリーズは走るカタログと言われたりもしますが、ツーリストトロフィーも良い意味でまさにそんな感じがしますね。
まだ時間の都合上あまりプレイできてはいないので、これからちょっとずつ楽しんでいきたいと思っています。
2015年2月13日金曜日
資生堂 タクティクス
こんばんは、ろど☆すたです。
ひょんなことから幼い頃の記憶が蘇ることってありませんか。
大した事ではないんですが、なんとなくそういえばあの時あんなことがあったなっていう。
幼い頃、よく洗面所でこんな特徴的な容器が転がっている光景を見かけた記憶がありました。
資生堂の男性用化粧品ブランド、タクティクスシリーズ。
1978年の登場から現在でも販売されている息の長い商品で、コロン、ヘアムース、アフターシェーブなどなど多岐に渡ったラインナップが展開されています。
1970年代、まだ男性が香水をつけるなんて考えられなかった時代に登場し瞬く間に日本のみならずニューヨーク、パリそしてミラノにまで広まった、いわば男性用香水のパイオニア的存在でもあるタクティクス。
"男の香りはスリリングな方が良い"
"香り、女には見えるものらしい"
"香りはちょっとした天国だ"
このようなちょっとトガッたキャッチコピーも追い風となり、いわゆる不良に人気のブランドにもなったそうな。
むしろ資生堂の戦術通り、まさにタクティクスだと言われています。
(Tactics - 戦術)
それ故に昨年実写映画化され再び話題になった、1986年の少女漫画「ホットロード」にも"タクティス"として登場しているんだとか。
私も映画ホットロード、映画館で見ました。
ハリセパにナポミラ、フォーサイトにBEETテールのCBRは、当時バイクに興味のない女子中高生にも格好良いと思わせるほどだったそうです。
ただ、原作や有志による"春山仕様"からも見て取れるように、Ⅰ型のコムスターホイールを赤に塗装したのが真の"春山仕様"なんですよね。
一部ではピンクという説もあるようですが。
絶版かつ人気車故仕方ないのかもしれませんが、映画ホットロードのCBRはⅡ型のスポークホイールを赤に塗装したものになっていました。
実際コムスターホイールは素人による分解はメーカーから推奨されておらず、希少価値もあるためいろいろな事情があったんでしょう。
そして尾崎豊の"OH MY LITTLE GIRL"も良い曲ですしマッチしていたと思いますが、私個人的にチェッカーズが好きなのもあって、藤井フミヤがホットロードをイメージして書いたと言われている、"Jim & Janeの伝説"だとなお良かったなと思いました。
チェッカーズの解散には色々な理由があるとされていますし、最近になってようやく藤井フミヤがチェッカーズ時代の楽曲をテレビやライブで歌うようになりましたが、なかなかチェッカーズ名義での使用は難しい事情があるんでしょうね。
話が大きく脱線してしまいました。
私が幼い頃に洗面所で見かけたタクティクスはコロンだったのかアフターシェーブだったのかすら定かではありませんが、恐らく父のものだったんでしょうね。
もちろん香りも覚えているわけではないんですが、この特徴的な容器をおもしろいなと思った記憶はしっかり残っています。
最近は絶版になっただのオンラインショップでしか入手できないだのと言われているようですが、資生堂の店頭や一部のお店でも普通に売っているようです。
甘い柑橘系な香りのなかにグリーンフローラルの少し苦味の入ったような言葉では言い表しがたい特徴的な香りがタクティクス。
今でもこの香りを鼻にすると当時を思い出すという人が多いようです。
人間、視覚の記憶より嗅覚の記憶の方がより強烈な気がしますね。
風に香るTacticsが俺の胸を締め付けるAngel
2015年2月5日木曜日
The 10 Worst Songs of the 1980s
こんばんは、ろど☆すたです。
アメリカで歴史ある情報誌「Rolling Stone」の日本版「Rolling Stone JAPAN EDITION」がバイト先の系列企業であるセブン&アイ出版から発売されていることを知り驚きました。
そんなRolling Stoneが'11年10月に行ったReaders' Poll 、読者投票企画である"The 10 Worst Songs of the 1980s"がとても興味深く面白いものでした。
80年代の洋楽と言えばまさに名曲揃いで、日本でも数多くのシングル、アルバムが発売されています。
中では現在でもテレビ番組やCMなどに起用されている曲も多く、興味が無い人でも一度は耳にしたことがある、といった曲がたくさん存在しますね。
しかしながらヒットした反面、音楽性や内容が悪いといったところや、本人や楽曲自体に何ら問題はないものの、"最低ソング"が存在するのも事実です。
そこでRolling Stoneは読者に投票を募り、ワースト10を作成したんですね。
その中でも特に面白いと思ったものをピックアップしてみました。
10th - Never Gonna Give You Up / Rick Astley (1987)
(邦題 - ギヴ・ユー・アップ)
イギリスの歌手、リックアストリーの事実上のデビューシングルである"Never Gonna Give You Up"。
甘いマスクとは裏腹に太い声が特徴の所謂"見た目と声が違う"歌手の有名なヒットソングで、日本でもバブル全盛期のディスコブームに乗り、大ヒットを遂げました。
内容的には幼馴染(?)に愛を告白する至って普通のラブソングなんですね。
Never Gonna Give You Up ―君のことを諦めたりしないから、といったような捉えようによっては少しストーカー気質のような気もしないでもないですが。
しかしそれが原因でランキング入りというわけではありません。
アメリカ版2ちゃんねるとも言われる"4chan"という画像掲示板にて、エロ動画等のリンクに見せかけてリックアストリーのギヴ・ユー・アップの動画に誘導するという所謂釣り行為"Rickroll"が流行し、あまりにもそのイメージが強くなりすぎた事がランクインの理由のようです。
日本でいうところのバーボンハウスの動画版のようなものだとか。
もともと釣り動画に使われていたものは、車輪付きアヒルのおもちゃで"duckroll"と呼ばれていた事から"Rickroll"と名付けられたそうです。
ただ、何故この釣りが流行した当時(2007年)、ブレイクしていたわけでもないリックアストリーが使われたのかは謎ですが。
しかしこれがリックアストリーの再ブレイクの火付け役となり、自身も度々ネタにするんだとか。
まさに本人にも楽曲にも関係のない部分から最低ソングランクインを果たした曲ですね。
8th - Mickey / Toni Basil (1982)
(邦題 - ミッキー )
アメリカの歌手であり振付師のトニーバジルの大ヒット曲"Mickey"。
米ビルボードチャート1位、英シングルチャート2位とまさに大ヒットと呼べる一曲です。
後に日本でもガレッジセールのゴリが松浦ゴリエとしてカヴァーしてブームを巻き起こした曲ですが、実はトニーバジルもカヴァーだったんですね。
1979年、イギリスの音楽グループであるレイシーが発表した"キティ"と呼ばれる曲が原曲と言われています。
しかしながらこのキティはヒットしませんでした。
そこでタイトルを女性の愛称であるキティから男性の愛称であるミッキーに変え、歌詞も恋する乙女を描いたものに差し替えて、トニーバジルがカヴァーしたところ大ヒットとなりました。
このMVはトニーバジル自身が振付をし、自ら踊り、そしてビデオの制作まで担当したんだとか。
逆にそれが仇となり、またMVもあまりスタンダード化していない時代に低予算でつくられたモノが色々なところで何度も何度も流された結果、むしろイメージを悪くしてしまった結果のランクインのようです。
注目を浴びるものに一定数のアンチが存在するのは仕方のない事なんでしょうか。
またトニーバジル自身、所謂一発屋扱いされている点もランクインの理由となりそうです。
7th - Don't Worry Be Happy / Bobby McFerrin (1988)
アメリカのジャズ歌手、ボビーマクファーリンの声だけで多重録音で制作された"Don't Worry Be Happy"。
楽器を一切使用していない曲では初となる米ヒットチャート一位を記録し、なんとグラミー賞でも最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀男性ポップボーカル賞の3冠を達成するなど、世界的に認められた名曲でもあります。
JTの缶コーヒー、RootsのCMソングにも起用されていた事があり、耳にした事があるという人も非常に多いのではないでしょうか。
話が脱線してしまいますが、Rootsや桃の天然水等で有名なJTが今年7月末をめどに飲料業界から撤退する旨が発表されました。
缶コーヒー業界は、近年のコンビニコーヒーの普及により徐々に売上も落ちてきているようで、本業がタバコであるJTからすれば、ちょうどいいきっかけになったのかもしれないですね。
1988年から飲料業界に参入し、数多くのヒット商品を販売していたJT。
私個人的にはRootsの缶コーヒーは好きだっただけに非常に残念です。
さて、楽曲の方に戻りますがなぜこの曲が最低ソングに選ばれてしまったのか。
トニーバジル同様、ボビーマクファーリンにはこの曲以外にヒットソングがないという一発屋、という点が理由だそうです。
米Rolling Stoneの読者は一発屋に厳しいのだとか。
また、近年ボビーマクファーリンがこの曲を歌唱しないのもランクインの理由だと考えられそうです。
2nd - The Final Countdown / Europe (1986)
(邦題 - ファイナル・カウントダウン)
(邦題 - ファイナル・カウントダウン)
スウェーデンのヘビィメタルバンド、ヨーロッパの最大のヒットソング"The Final Countdown"。
なんと全世界でのシングル販売枚数累計780万枚、25ヶ国のチャートで1位を獲得したという、当時知らない人を探すほうが大変なんじゃないのかというレベルで売れた曲がこのファイナルカウントダウンです。
ちなみに何をカウントダウンしているのかというと、地球を離れ金星へ向かうためのカウントダウンなんですね。
わりと曲は知ってても、内容までは知らない人が多いそうな。
この大ヒット曲が最低ソング第2位に選ばれてしまった理由に、腹が立つほどに覚えやすくキャッチーなキーボード、最高にいらいらさせられるだけの曲、といったような内容があげられていました。
確かに初めてファイナルカウントダウンを聴いたとき、イントロからのキーボードのメロディーは一回にして覚えてしまうほどの強烈なインパクトだったのを覚えています。
またEuropeの前身であるForceの頃と比べて、音楽性のポップ化が著しく進みかつてのファンからは認められていない部分もあるのかもしれないですね。
現にファイナルカウントダウン前後にバンド内での脱退者が多くいたようです。
1st - We Built This City / Starship (1985)
(邦題 - シスコはロックシティ)
堂々の1位(?)はアメリカのロックバンド、スターシップの代表曲でもある"We Built This City"。
スターシップはもともとジェファーソンエアプレインというロックバンドが起源であり、後に改名したジェファーソンスターシップからさらに派生したバンドです。
というのもメンバーの入れ替わりが激しく、最終的にオリジナルメンバーであるポールカントナーと、途中から加入してきたメンバーが対立し決裂。
その結果ジェファーソンスターシップというジェファーソンエアプレインの後継に当たるバンドと、もとはジェファーソンスターシップだったもののオリジナルメンバーが一人もいなくなり、再出発をしたスターシップというバンドが現在も存在することになっています。
そのジェファーソンエアプレインというバンドは1960年代を代表するサイケデリックバンドであり、演奏力、創作力共に素晴らしく、1996年にはロックの殿堂入りを果たしているほどのバンドでした。
そんなジェファーソンエアプレインの復活かと思われたスターシップでしたが、実際は当時のオリジナルメンバーは誰一人とおらず、コンセプトも一転(スターシップ結成)当時の流行であるエレクトロポップをふんだんに取り入れた楽曲を数多くリリースしヒットした中でも最も評判の悪い曲がシスコはロックシティでした。
ジェファーソンエアプレイン時代からのファンとしてはもちろんこんなの認められない、というのもあるのでしょうが、さらにはこの曲の歌詞にも最低ソング1位に輝いてしまう理由がありました。
We built this city ―僕らがこの街をつくった
We built this city on rock and roll ―僕らがロックンロールの街をつくったんだ
We built this city on rock and roll ―僕らがロックンロールの街をつくったんだ
かのジェファーソンエアプレインのメンバーでもなく、後発であるスターシップが一体何を言っているのだ、と。
そしてこの曲をつくったのはスターシップのメンバーですらありませんでした。
80年代の最低ソングだけでなく、アメリカの音楽雑誌「Blender」の"音楽史に残る最も酷い歌詞50"でも第1位に輝いています。
ポップで、良い意味で'80年代を代表する楽曲だと思うのですが、境遇を考えるとこのヒットを歓べないファンもいたということでしょうか。
普段よく耳にする1980年代の洋楽たちでしたが、いろいろな捉え方があるのだと非常に面白く感じました。
同じ'80年代の邦楽と洋楽を比べたときに、洋楽のクオリティの高さに毎度驚くのですが、こういった見方も良いですね。
2015年2月1日日曜日
JR九州 305系
こんばんは、ろど☆すたです。
車やバイクの他に、あまり詳しくはないのですが鉄道も好きだったりします。
JR九州が新型通勤型車両305系を2月5日より順次筑肥線へ導入します。
この筑肥線は、福岡市西区の姪浜駅から佐賀県唐津市の唐津駅、同市山本駅から佐賀県伊万里市の伊万里駅までを結ぶ、総延長68.3kmに及ぶ路線です。
電化されているJR九州の路線では、関門鉄道トンネルとこの筑肥線のみが直流電化区間となっています。
なぜそのような路線になったのか、直流電化運行をしている福岡市営地下鉄と相互運転を行うからなんですね。
姪浜駅から福岡市営地下鉄空港線の福岡空港駅まで、JRの車両が直通運転をするため、直流専用車両が必要になるのです。
現在福岡空港駅まで乗り入れているJR九州の車両は、103系1500番台と呼ばれている国鉄時代に、同じく市営地下鉄相互運行の為につくられたものと、2000年のダイヤ改正に伴い、前述の103系1500番台では不足となるためにつくられた303系と呼ばれる2つの電車で構成されています。
103系1500番台は103系の中でも最末期の車両。とはいえ初運行は既に31年も前になります。
JR九州お得意の旧車改造で、内外装共に古臭さを感じさせませんが、どうしても基本構造の古さは否めず、ワンマン運行にも対応していません。
特に最近では乗り入れ先の地下鉄路線でのトラブルも多く、運行に支障をきたしてしまう事もあるようで、いよいよ一部の103系1500番台は引退に追い込まれてしまいました。
そこで103系1500番台の代替用車両として開発されたのが305系。
こちらの画像はJR九州の交流電化区間専用近郊型車両の817系と呼ばれる車両で、通称”白カン”です。
通称の由来は単に白い缶だからです()
2000年に導入された303系は、817系より以前に交流電化区間に導入された813系と同じく、ステンレス無塗装ボディに赤の差し色が入っており、103系1500番台に近いカラーリングでした。
近郊型車両の813系→817系の順に習って通勤型車両も同じような配色になっているのかもしれないですね。
817系白カンと305系の大きな違いは、地下鉄路線に乗り入れるためにサイドがフラットなボディになっている点でしょうか。
また一応通勤型と近郊型故か、ドアの枚数が違いますね。
国鉄時代には通勤型は4枚ドア、近郊型は3枚ドアといった棲み分けがあったりもしたようですが、最近は4枚ドアの近郊型があったり、通勤型の基本はロングシートのみではあるものの、ボックスシートのものもあったりと明確な差別化は図られていないようです。
それ以前に福岡市営地下鉄が4枚ドアであるため、JRの車両も4枚ドアである通勤型を名乗っているのかもしれないですね。
ちなみにJR九州の通勤型電車は筑肥線を走る車両しかありません。
JR九州もここ数年、九州新幹線鹿児島ルートだとか観光列車だとかで大きな事業も多かったようですが、それも一段落し、817系以来14年ぶりの新車の導入ということで管内最新設備も見受けられました。
近年都市圏では当たり前の装備になっているようですが、JR九州では初となる車内扉上部の大型LCDモニターの実装。
従来の行き先表示だけでなく、ICカードの説明や広告、近隣の観光案内等を表示できるようになっているようです。
また、こちらも今となっては珍しくはない装備ですが、同じくJR九州では初の押しボタン式開閉ドアの実装が、筑肥線各駅のポスターで大々的に紹介されています。
私は主に817系が活躍する路線を利用しているのですが、博多や小倉といった主要都市よりも田舎に住んでいるために、駅で誰も乗降しないなんていう場面に出くわすことがよくあるんですよね。
冷暖房ともに無駄を感じますし、何より駅に止まるたびに今の時期ですと北風が入り込んできて寒いんです。
筑肥線に導入される305系も、乗降の多い区間は停車時間が長い時のみ、乗降の少ない区間は駅毎に押しボタン式開閉ドアとなるようで、これは今後他の車両にもぜひ追加実装して欲しい装備だと思います。
ちなみに817系2000番台、3000番台のこの片持ちロングシートは座りが心地が悪いことで、全国的にも有名だそうな。
近郊型電車故、長時間長距離利用する人も多いかと思わますが、実際座面のクッションが薄く、背面の背もたれも木で非常に辛いです。
JR九州の観光列車で有名なななつぼし等を手がけた工業デザイナー、水戸岡鋭治氏が手がけたそうですが、正直デザイン重視のあまり座り心地は二の次のように感じます。
305系も同氏デザインによるもので、通勤型車両故全車片持ちロングシートですが、先日の試乗会では817系とは比べ物にならないほどに座り心地が向上している、という感想を多く見受けられました。
JR九州の車両は、他JRに比べても個性が強く独自性があって、調べれば調べるほど面白いなと思います。
2015年1月29日木曜日
New Alphard/Vellfire
こんばんは、ろど☆すたです。
既に多方面で話題に上っていますが、およそ6年半ぶりにトヨタの主力ミニバンであるアルファード/ヴェルファイアのフルモデルチェンジが発表されてました。
以前トヨタの販売マニュアルのようなものがネット上に出回り話題を呼んだ、まさに"マイルドヤンキー"なるターゲットを的確に捉える事ができそうなフルモデルチェンジとなりそうです。
現行型はあくまでアルファードが上品さ洗練さをイメージしたデザイン、ヴェルファイアが力強さや先進性をイメージしたデザインと謳っているそうですが、新型ではむしろアルファードの方が押しの強いフロントマスクで力強さを感じます。
ネッツお得意の上下分割ヘッドライトやクリアテールが新型でもあしらわれていますが、個人的にはアルファードよりも全体的にまとまった印象を覚えました。
最近のトヨタ車のトレンドである大型フロントグリルですが、未だインパクトが強すぎるというか逆に高級感に欠けるような。
ちなみにアルファード/ヴェルファイアで尽きないネタといえば、リアのトーションビームサスペンション。
今となっては四輪独立懸架なんて言われても当たり前のように感じますが、トヨタ車としてはそうでない車も多くアルファード/ヴェルファイアに限ったことでもありません。
しかしながら新型では新たにリアにダブルウィッシュボーンサスペンションが採用され、晴れて四輪独立懸架となりました。
また直4モデルに採用されていた2400ccの2AZ-FEエンジン。多くのトヨタの中小型車に採用されていますがそのほとんどが中国トヨタで製造されているもので、非常に質が悪く一部車種で保証期間を延長するという異例の対応がとられたエンジンでした。
この点も新型では事実上の後継エンジンにあたる、2500ccの2AR-FEエンジンとなり燃費とともに耐久性も向上しそうです。
3500ccモデルは2GR-FEを継続採用。
新たに追加されるハイブリッドモデルも2AR-FXE(アトキンソンモデル)と2GR-FEの2排気量が用意されるようです。
もともと派手なデザイン故にDQN大喜びなんて言われていますが、TRDからリリースされるカスタマイズキットにマイルドヤンキーも驚きのパーツがありました。
驚異の6本出しマフラーです。しかもダミー。
もちろんこのマフラーカッターにエキゾーストパイプが繋がっているわけもなく、実際のマフラーはバンパーより内側で下向きに装備されています。
以前レクサスLSやトヨタマークXで、リアバンパーにマフラーカッターが一体型となったデザインが採用されたこともありましたが、こちらのTRDのエアロパーツはそもそもマフラーカッターですらなく、バンパーの一部なんです。
あくまでデザインなのでそれに突っ込んでも仕方がないのですが、直4モデルはエンジンのピストンの数よりマフラーの出口の方が多い計算になってしまうわけですよね。
二輪の集合管ならぬ分散管とでも言いましょうか。
関係無いですがSOHC単気筒2本出しチャンバーなんてものがあるのを思い出しました。
レッドモールという主にミニバイクのカスタムパーツをリリースしている会社の製品なんですが、エンジンの性能を極限まで引き出すためのマフラーを開発したところ、サイレンサーが一本ではうるさすぎるため、仕方なく2本出しにしてサイレンサーを2つ装備したそうです。
その真偽や実際の性能は私はわかりませんが、TRDのダミーマフラーと比べるのはあまりに失礼でしたね、すみません。
四輪の6本出しマフラーでは、クラウンやオデッセイ、H2なんかでもアフターパーツとしてリリースされてはいるようです。
それをカタログモデルで出してしまうトヨタ、TRDのマイルドヤンキー商法は流石と言ったところですね。
ちなみにホンダもマイルドヤンキー商法を謳っているようですし、公式DQNカスタムも今後増えていきそうな気もします。
新型アルファード/ヴェルファイアは2月7日発売です。
2015年1月25日日曜日
Honda Suzuki 110cc
こんばんは、ろど☆すたです。
一昨日23日に新型タクト、発売されました。
そのタクトが発表された16日金曜日、新型ディオ110も発表されていました。
デザインは現行ディオ110のキープコンセプトで、14インチのスクーターとしては大径ホイールを履き、アジアンチックなイメージです。
価格、発売日共に未定ですが、今春の発売を目処に調整中だそうな。
デザインこそ大きな変更点は見られませんが、注目は新開発エンジン。
次世代小型スクーター用エンジンであるeSP。その空冷版を新たに開発し、このディオ110に初めて搭載される予定です。
新型タクトを含む、PCXやリードといった近年のホンダの小型スクーターに搭載されているeSPは全て水冷だったんですね。
水冷と空冷を比べると、水冷の方がパワーが出しやすいというイメージがありますが、もともと数馬力の小排気量エンジンを載せた小型スクーターでは、そこまで違いがあるわけではなく、むしろ従来のスクーターの強制空冷の方が軽量化によるメリットのほうが多いようです。
また燃費や環境面でも、水冷より空冷の方が不利かと思われましたが、
排気量の違いはあれど現行水冷eSP搭載PCX125は53.7km/L、
空冷eSP搭載新型ディオ110は57.9km/Lと向上しているようです。
そしてこのディオ110を追うようにスズキから発表されたのが、アドレス110。
過去にスズキから販売されていたアドレス110の2stエンジンは、後にも先にも原付二種至上最高にして最速のエンジンとすら評されていました。
現に工場出荷時状態でゆうに100km/hを超えてしまうポテンシャルだったんだとか。
逆にアドレスV100とはかけ離れた大きく重いボディが残念ではありました。
そこで3月19日、V100の軽快さを併せ持つ新型アドレス110が発売されます。
実は昨年の9月にドイツで発表されてはいたようです。
ディオ110と同じく14インチタイヤにアルミキャストホイールと似た印象を受けますね。
スズキの50ccスクーターは国産がウリではありますが、こちらのアドレス110はインドネシア生産となるそうです。
なお現行ディオ110は中国生産。
近年は海外生産が多いのはもはや仕方のないことなんでしょうか。
ちなみに大径ホイールにすることによって安定性や取り回し、乗り心地が向上するといったメリットももちろんありますが、日本以外のアジア圏だけでなく欧州でもそれが主流のためこういったデザインが増えてきているように思えます。
逆に12インチのスクーターというのはむしろ珍しい存在でもあるそうな。
14インチによるデメリットはインチが大きくなる為幅が細くなる点と、スクーターのウリでもあるメットインがどうしても小さくなってしまう点があげられます。
新型アドレス110は装備重量97kg。現行ディオ110は103kg。
アドレスはクラストップの軽量さを謳ってはいますが、同じスズキのレッツ4は68kgと30kg近く重く、やはり往年のアドレスV100のような驚異的な軽さは実現できなかったようですね。少し残念です。
燃費も51.2km/LとホンダのeSPには及びませんが、SEPと呼ばれる高効率エンジンを搭載し、ハイカムの恩恵も受け現行ディオ110の8.4psを上回る9.1psを発生させます。
そしてなんといっても驚きなのが205,200円という価格。
現行ディオ110と全く同じ価格設定です。新型ディオ110がどう出るかも楽しみです。
最近は50ccスクーターでも20万円を超える車両が当たり前ですから、とても安く感じられますよね。
原付とバイクのいいとこ取りとも言われる原付二種。
ここ数年は非常に熱い市場となっていますし、スクーター好きな私からするととても今後が楽しみでもあります。
2015年1月22日木曜日
クロネコメール便
こんばんは、ろど☆すたです。
今日、ヤマト運輸よりメール便廃止の発表がありました。
セブンイレブンでバイトしている事もあり、よくメール便を扱います。
メール便を利用した事がある人はわかるかと思いますが、角2の封筒で厚さ1cm以内なら82円で配送してくれるというとても安価なサービスなんです。
ただし対象は、パンフレットやカタログ類といった補償の必要がなく、万が一届かなくても受取人が損失を被らないモノに限られます。
万が一配送の途中で紛失したり破損したりした場合は、再送料のみ補償してくれます。
つまり配送料以上の補償が必要な物は対象外なんですね。
しかしながらオークションやマーケットプレイス等での商品の発送等に、配送料の安さから多用されてしまっているのが現状だそうな。
定期的にネットでも「メール便で破壊されました。」「一切補償もなく泣き寝入りです。」といったような内容の書き込みが話題になっていますね。
補償の対象外だから当たり前の事なんですがね。
また、信書ももちろん対象外なのですが、企業間でも頻繁に使われており訴訟問題になったケースもあるようで。
信書はメール便で送ると郵便法違反になってしまうんです。
メール便廃止にあたっては、類似サービスを行っている郵政の上場に際しての裏でのゴタゴタや、配送料の安さ故儲けがないから、といった様々な憶測が飛んではいますが、きちんとサービスの概要を理解せずに利用し、さらにそれに対してあたかも自分には非がないような被害者面する利用者が多いことが少なからずも関係していると私は思います。
廃止後の今年4月以降は、現在のメール便で間違って利用されている小さな荷物や、トレーディングカード等にも対応した宅急便よりも安価なサービスへ移行する予定だそうです。
セブンイレブンバイトからすると、取り扱うサービスがむしろ増えるような気もしますね。
大げさかもしれませんが、ある意味利用者のせいで潰れたサービスとも言えるかもしれませんね。
2015年1月21日水曜日
Honda Tact
こんばんは、ろど☆すたです。
兼ねてから、というより最近の事ではあるんですが、この事を書きたいが為にブログを再開したようなものでもあります。
ホンダタクトのネーミングが復活しました。
ホンダのタクトといえば1980年代に一世を風靡したと言っても過言ではない原付スクーターですね。
また最近でも一部マニアや旧車會などでは絶大な人気を誇っています。
今でもカスタムベースに人気の二台目タクトのクレージュ仕様。
フランスのファッションデザイナー、アンドレ・クレージュがデザインした事からクレージュタクトとネーミングされているそうな。
じゃんけんミラーがいい味出していますね。
タクトといえばこういったシャープなイメージが強いですが、新型は晩年の丸みを帯びた物になっているように思えます。
メットインタクトが発売された頃、敢えてメットイン機構を売りにしている事からもわかるかとは思いますが、50cc以下もヘルメットの着用が義務付けられたんですね。
それ以前はいくら30km/h制限とはいえノーヘルで乗れていたと思うと、今考えれば非常に恐ろしいです。故に死亡事故も絶えなかったようですが。
新型で全盛期のシャープなデザインではなく敢えて晩年の丸みを帯びたデザインとなったわけは、幅広いターゲット層をイメージしていることから来ているようです。
新型タクトは昨年の2月にデビューしたダンクをベースに作られています。
そのダンクのターゲットは若年層。
プレミアムスニーカーという開発コンセプトの下、若者のライフスタイルをリサーチし商品化した一台なんだとか。
確かにスクーターらしからぬバーハンドルや、専用設計のホイールなど熱は感じられますよね。
現に私の知り合いが最近購入したんですが、同じホンダの現行車であるDioやTodayと比べて高級感がとても感じられました。
またバーハンドルのスクーターっていうのは想像以上にスタイリッシュです。少し欲しくなりました。
ダンクがこのようなコンセプト故、タクトには落ち着いたイメージを与えたかったんでしょうね。
ホンダは四輪二輪問わず、過去の名車の車名を復活させているのを最近よく見かけます。
タクトもその一つなんでしょう。
一番直近の例ですと四輪のNシリーズがありますが、N Oneはともかくそこまで過去のNを意識しているようには感じられませんでした。
単にネームブランド効果を狙っているのかな、と。
かと言ってタクトが面白味がないわけではありません。
ダンク、タクトに搭載される水冷4stOHC単気筒エンジンは、ホンダのeSPと呼ばれるスクーター専用に開発された低燃費エンジンなんですね。例えるならマツダのスカイアクティブのようなイメージでしょうか。
なんでもeSPにはアイドリングストップ機構が搭載されているんだとか。
果たして二輪でアイドリングストップってどうなんだろうっていう感じですが、現に燃費向上には一役買っているそうですよ。
カタログ値80km/lという驚異の数値。
実走行は仮に半分でも40km/lですよ、普段25km/l行かない2st50に乗ってる私からすれば驚愕です。
そんなeSP、4.5psを8,000rpmで発生させます。
現行Dioに載っている3.8psエンジンは、国内3社の中で最遅と酷い言われようですが、こちらはどうなんでしょうか。
機会があればダンクの方にでも乗ってみたいですね。
新型タクトの発売は今週金曜の23日。
172,800円。廉価版が159,840円。
当時のタクトと比べると2倍近いなんて話も出ていますが、時代が違うので仕方のない事です。
現在の50ccで見るとむしろ安い方ですね。
ベースのダンクは20万強しますし。
制約の多さ故か規制のせいなのか、はたまたバイク離れなのか、非常に寂しい50cc市場を再びタクトが盛り上げてくれると良いですね。
細々とながら国内3社、昔からのネーミングで50ccをリリースし続けている事は素直に素晴らしいと思います。
ちなみにベトナム生産だそうな。
172,800円。廉価版が159,840円。
当時のタクトと比べると2倍近いなんて話も出ていますが、時代が違うので仕方のない事です。
現在の50ccで見るとむしろ安い方ですね。
ベースのダンクは20万強しますし。
制約の多さ故か規制のせいなのか、はたまたバイク離れなのか、非常に寂しい50cc市場を再びタクトが盛り上げてくれると良いですね。
細々とながら国内3社、昔からのネーミングで50ccをリリースし続けている事は素直に素晴らしいと思います。
ちなみにベトナム生産だそうな。
2015年1月19日月曜日
January 19
404 Not Found
お探しのページは見つかりません。
こんばんは、ろど☆すたです。
という挨拶をするのっていつ以来になるんでしょうか。
実は以前楽天で数年間ブログをやっておりました。
当時はTwitterやFacebookといったSNSがあまり普及しておらず、ブログサービス全盛期の頃でした。
しかしながら次第にブログという文化も廃れて行き、一人、また一人と楽天から人が去って行き、結局私も更新が滞ってしまいました。
楽天ブログから離れて二年あまりになりますが、なぜだか最近無性にブログというか日記をつけたい衝動に駆られるんですね。
楽天ブログ時代から、一応車やゲームといったテーマはありましたが基本的に自己満足なほぼチラ裏的な記事ばかりでした。
今回またこのBloggerの方でもゆるーく、日記帳的な感じでやって行こうかなと思っております。
イマイチまだBloggerのシステムを理解できていないので、質素なブログではありますが、チマチマと更新して行ければなと考えてます。
こちらはあくまでブログですので、楽天ブログ時代のように(?)そこそこ丁寧な言葉で、そこまで過激でない内容を予定しています。
基本的に私が個人的に興味が有る事象を適当にまとめる為に使っていこうかなというイメージです。
あとは少しはまとまな文章を書けるような、練習といいますか、そんな感じです。
誰が得するかもよくわからないようなブログになるかとは思いますが、たまにでも覗いて頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。
登録:
コメント (Atom)